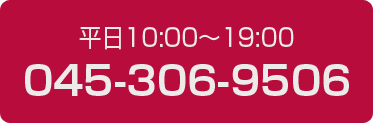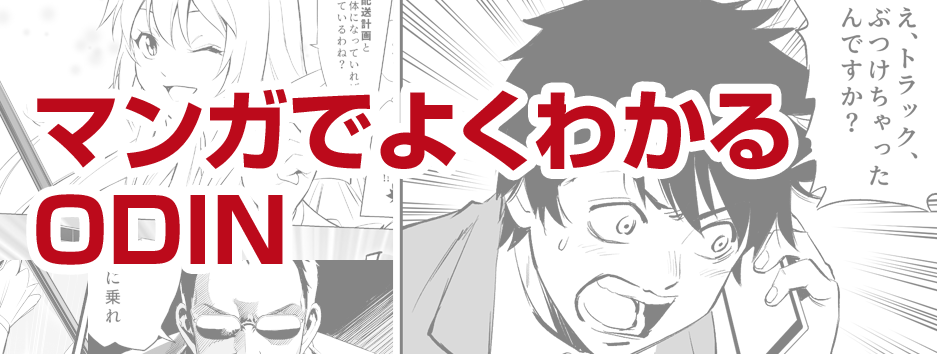運送業の生産性をアップするためには、車両を効率よく稼働させることが必要不可欠。それを妨げている深刻な問題のひとつが「トラックの待機時間」です。
「トラックの待機時間」とは
集荷先や配送先、物流センター、自車の倉庫などで発生する待ち時間のこと。荷物の積み込みや荷下ろしの順番を待たなければならなくなることが、頻繁に起こっているのです。しかも、突発的なトラブルではなく、日常的に待機時間が発生しているケースも少なくありません。かつては、大きな物流センターにトラックが長蛇の列をなし、社会問題となったことも……。

そもそも、トラックの待機時間はなぜ発生するのでしょうか?
原因はひとつではなく、複数の要因が組み合わさることで問題が複雑化しています。
主だった原因は、以下のようなものです。
バース(荷捌き場)の数が少ない
→ トラックが荷物を積み下ろしするための場所が少なく、順番待ちが発生する
バースが「到着順」でトラックを受け付ける
→ 時間で約束ができないため並ばなければならず、長時間の待機が発生することも
配送(荷受け、届け先)の時間調整がうまくできていない
→ 約束の時間に行っても、前の作業が終わっておらず待機する、など
時間の指定があいまいで、現場で場当たり的な調整をせざるを得ない
→ 「午前中」など時間の幅が広い指定だと、現地に着いてからの状況で対応せざるをえず、待機時間が長くなりがち
トラックの待機時間は、そのままドライバーの労働時間となります。労働が長時間化することは、ドライバーの健康面、生活面に悪影響を及ぼしますし、過酷な労働環境を若者が敬遠することでドライバーの高齢化にもつながっています。事業者にとっても人件費や車両費などのコストが増えますが、待機時間にかかるコストは運賃に反映しにくく、事業者にとってもドライバーにとっても負担ばかりが増える問題となっているのです。
2023年に経済産業省、農林水産省、国土交通省の3省が合同で制定した『物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン』では、荷待ちと荷役作業にかかる時間を計2時間以内とするルールを明記。さらに、2時間の目標を達成した事業者には、目標時間を1時間以内に設定することが求められています。
ところが、2024年に国土交通省が行った調査によれば、「荷待ち時間」の平均は1時間28分、積み下ろしを行う「荷役時間」は平均1時間34分、計3時間2分とルールには遠く及ばない実情が浮き彫りになりました。なお、同様の調査は2020年にも実施しているのですが、そのときは荷待ち時間が1時間34分、荷役時間が1時間29分、計3時間3分でしたので、ガイドライン制定の前後でほぼ変わらず横ばい。トラック待機の問題が、改善がひじょうに難しい課題であることが明確になっています。
事業者としてできる対策はまったくないのか、と言えば、そうではありません。経験と勘に頼って運用するのではなく、システムによる管理や可視化が不可欠です。
事業者として取り組める対策
物流センターや倉庫などに到着したトラックがバースに誘導されるまでのプロセスを見直す
→ 受付や案内、誘導にかかる時間を少しでも減らすことで、待機時間は短縮できます
荷物の積み下ろし作業の効率をあげる
→ バースはじめ荷下ろし場所の動線を改善し、作業の手順や人員を見直す。同時に、手でひとつひとつ荷物を積む「バラ積み」から、パレットやフォークリフトを使った積み下ろしにすることも、待機時間を大幅に短縮できる可能性が高い
管理システムを導入することで、バースの空き状況やトラックの位置を可視化する
→ バースの空き状況をリアルタイムで把握できれば、トラックを無駄なく誘導可能
トラックの位置情報がリアルタイムで判れば、倉庫側も早めに準備ができて待ち時間を減らすことができる
ODINが変える、現場の“待つ”を減らす仕組み
ODIN リアルタイム配送システムは、直感的でシンプルに使える配送管理システムながら、待機時間削減に大きく貢献することができる機能が搭載されています。
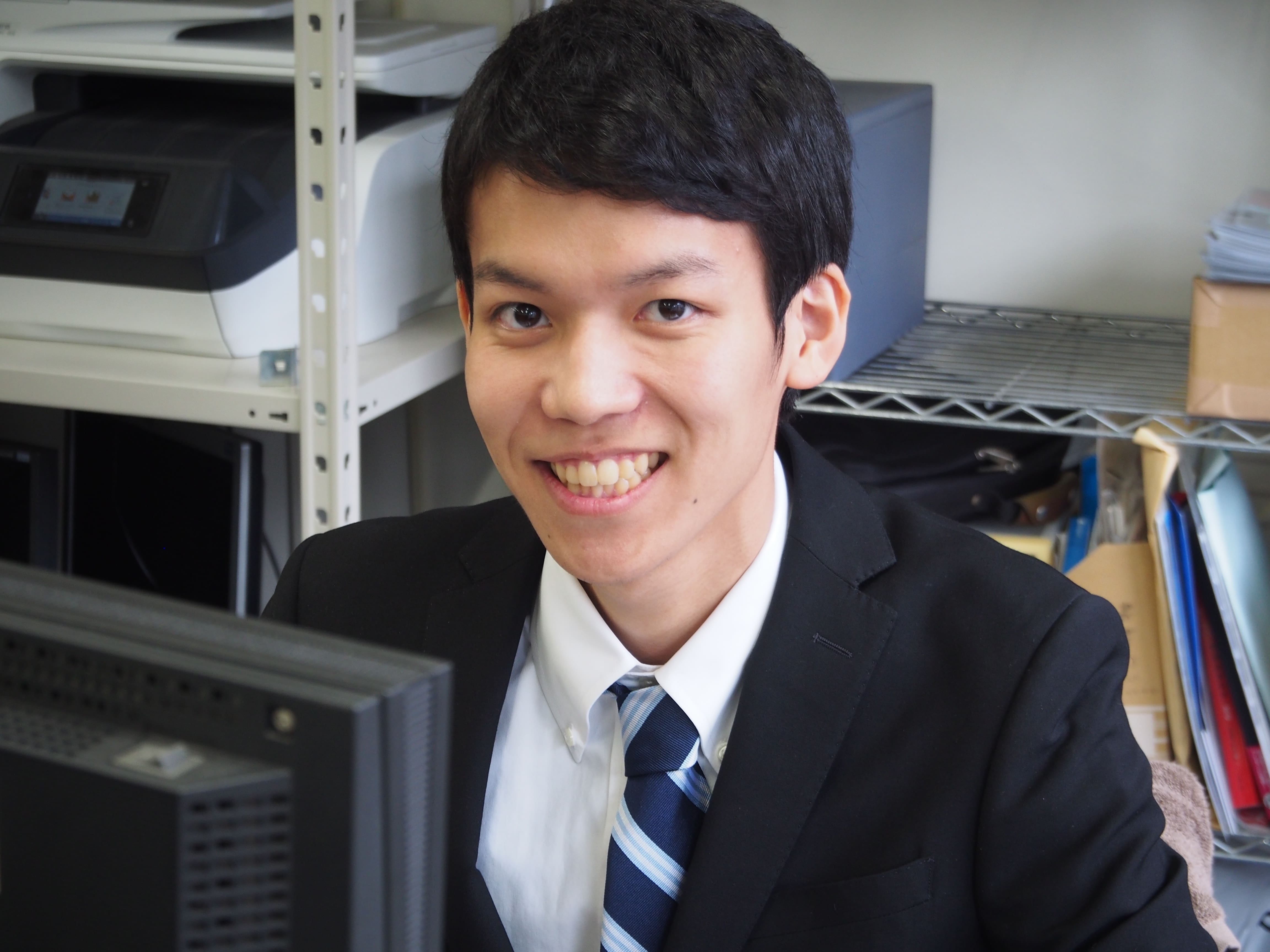
①位置情報の管理
トラックの位置情報を管理することで、なんの荷物を積んでいる車両がどこにいるのか、リアルタイムで把握。倉庫や物流センターへの到着時刻などをかなり正確に予測、管理できます
②設定したエリアにトラックが入ってきた場合の通知機能
工場や倉庫から設定した半径内にトラックが入ってきた場合、自動で通知が届くため、バースの状況と合わせて荷物の積み下ろしの準備をはじめつつ、スムーズにバース案内をすることができます
③配車機能
ドライバーのスケジュールや配送指示をデジタルで一元管理でき、行き先ごとの移動時間や距離を自動で計算。従来Excelや手書きで行っていた配車業務を効率化し、計画的な運行によって待機時間の削減につなげることができます。
まとめ
トラック待機時間の問題は、物流業界全体の問題です。ドライバーのマンパワーに頼るのではなく、問題となっている事象を細かく分析して可視化し、自動化・仕組化することで、解決していかなくてはいけない問題です。運送業者はもちろん、荷主や配送先がシステムを活用して連携し、業務の見える化・仕組み化を進めていくことで、はじめて解決の糸口が見えてくるのです。